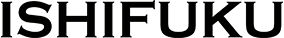【小菅努氏】金投資家にとっての錬金術の考え方 ~金を作り出すことはできるのか?~
- #貴金属投資の基礎知識
2025年08月20日
いしふくコラムでは、読者の皆様への情報提供の一つとして、2025年より貴金属に関する四方山話や相場解説などを専門家に執筆いただきます。 専門家の深い知見に触れ、貴金属への興味・関心を持っていただければ幸いです。
今回は、マーケットエッジ代表 小菅努氏にコラム「金投資家にとっての錬金術の考え方 ~金を作り出すことはできるのか?~」を執筆いただきました。

1976年千葉県生まれ。筑波大学第一学群社会学類卒。商品先物取引・FX会社の営業部、営業本部を経て、同時テロ事件直後のニューヨークに駐在してコモディティ・金融市場の分析を学びながらアナリスト業務を本格化。帰国後は調査部門責任者を経て、2016年にマーケットエッジ株式会社代表に就任。商社、事業法人、金融機関、個人投資家向けのレポート配信業務、各種レポート/コラム執筆、講演などを行う。
金投資家にとっての錬金術の考え方 ~金を作り出すことはできるのか?~
執筆日:2025/08/18
「錬金術」は実現している?
「錬金術(れんきんじゅつ)」と聞くと、多くの人は古代から中世にかけて世界各地で流行した疑似科学だと考えるかもしれません。錬金術とは、ベースメタル(鉄や銅など)から貴金属(主に金)を作り出そうとする試みです。かりに錬金術が本当に実現しているのであれば、金の持つ希少性は大きく変わることになります。
しかし、現代科学において錬金術は、もはや完全な「夢」ではなく、すでに一部で実現していることをご存じでしょうか。
1980年にはアメリカのカリフォルニア大学バークレー校の粒子加速器において、ビスマス(ベースメタルの一種)を金へ変換することに成功しました。また、今年(2025年)5月には欧州原子核研究機構(CERN)が大型ハドロン衝突型加速器(LHC)を使った日本の広島大学なども参加したプロジェクト「ALICE」の実験で、「鉛から金を作り出すことに成功した」と発表し、国内メディアでも大きく報じられました。鉛の原子核にある陽子の数が82個に対して、金は79個のため、理論上は鉛の原子核から3個の陽子を奪えば、金を合成できることになります。

このような「現代版錬金術」は金投資家にとっても興味深いものですが、現時点では金の需給・価格環境に大きな影響を与えるものにはなっていません。「錬金術に成功」と聞くと、金は大量にあるベースメタルと同等の存在になったようにも思えますが、現実の金市場においては、ほとんど影響が生じていません。
金価格が反応しない理由 ~科学的成功と商業的成功は違う~
この種の実験で注目すべきは、1)本当に実験に成功したのか、2)どの程度の量が得られたのか、3)どの程度のコストがかかったのかの3点です。
例えば、CERNの実験では2015年から18年まで4年間の実験で生み出された金は29ピコグラム(ピコは1兆分の1)です。実験には成功しましたが、原子レベルの話のため、生成できる量がごくわずかなうえ、すぐに消滅してしまうため、回収も不可能です。科学的には大きな成果ですが、商業的な活動としてはまだほとんど意味がありません。実用レベルの金は生み出せていません。
7月には米スタートアップ企業マラソン・フュージョンが、核融合のプロセスを応用して、水銀から金を生み出す方法についての論文を公表し、「錬金術を見つけた」と主張しています。核融合反応で生じる中性子を利用し、水銀の原子核の中性子の数を変化させることで、金を生成するしくみとされています。この件を報じた英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)は、出力100万kwの核融合発電で、年間5,000㎏の金が生み出せる可能性があるとしています。ただし、この論文に対する専門家の検証はこれからです。中性子の数が安定しない金が生み出される可能性も指摘されています。

また、自然界では、金は星の爆発などの天文現象で生成されたとみられるため、宇宙のどこかには大量の金を含む星が存在するのかもしれません。火星と木星の間にある小惑星「サイキ」は金などの金属を多く含むとみられていますが、米航空宇宙局(NASA)が2023年に打ち上げた探査船が2029年8月に到着する予定です。仮に金の存在が確認されても、地球上に持ち帰ることは困難です。ただし、人類が探査できる範囲内に大量の金が存在する可能性を示す点で、非常に注目されます。
金価格の高騰で「錬金術」への挑戦は活発化する見通しですが、現時点では金投資家が過剰に警戒する必要はないでしょう。ただ、過去に錬金術の研究は、硝酸や塩酸など現代社会でも重要な物質を多く生み出してきました。錬金術そのものが実用化されなくても、その過程で未来を大きく変える新素材や新技術が生み出される可能性は十分にあるでしょう。
- 本コラムは貴金属に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の購入・勧誘を目的としたものではありません。
- 本コラム掲載の文章は、全て執筆者の個人的見解であり、当社の見解を示すものではありません。また、文章の著作権は執筆者に帰属しており、目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。
- 本コラムの情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、当社は一切責任を負いません。実際の投資などにあたってはお客様ご自身の判断にて行ってください。
- 掲載内容に関するご質問には一切お答えできませんので、あらかじめご了承ください。